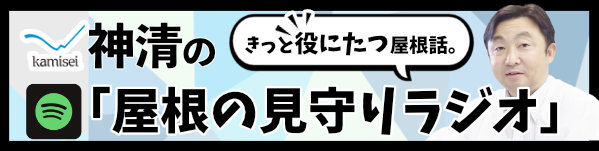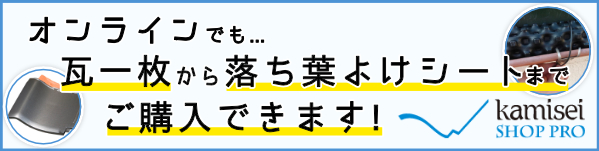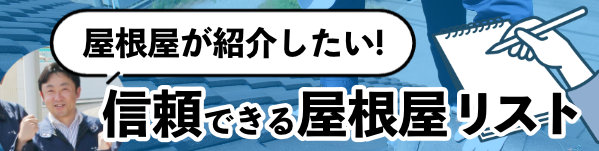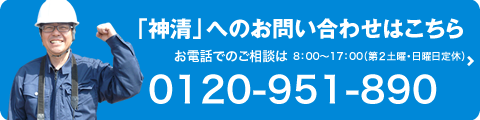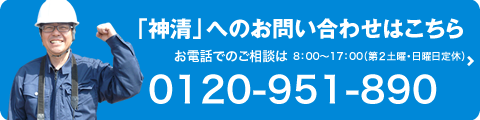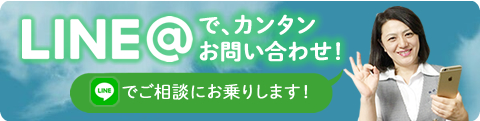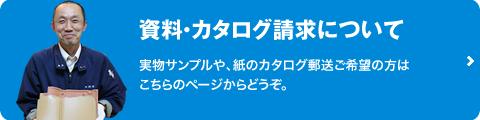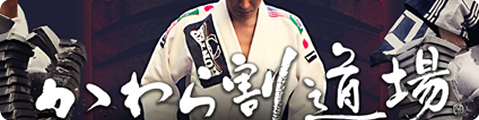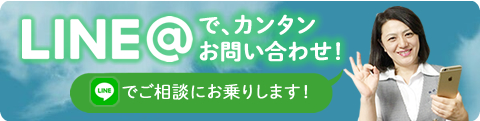目次
- 雨漏りしたらまずどうする?バケツを使った応急処置
- 雨漏りしたらまずどうする?タオルを使った応急処置
- 雨漏りしたらまずどうする?ブルーシートを使った応急処置
- 雨漏りしたらまずどうする?吸水シートを使った応急処置
- 雨漏りしたらまずどうする?防水テープを使った応急処置
- 雨漏り量が多いとき・広範囲に雨漏りしたらどうする?
- 雨漏りを見つけたらどうする?原因調査の方法
- 雨漏りを見つけたらどうする?目視で原因調査
- 雨漏りを見つけたらどうする?散水で原因調査
- 雨漏りを見つけたらどうする?赤外線サーモグラフィで原因調査
- 雨漏りを見つけたらどうする?ドローン撮影で原因調査
- 雨漏りを見つけたらどうする?解体で原因調査
- 雨漏りしたらどうする?避けたいNG行動
- 【まとめ】雨漏り被害が広がる前に、適切に対応しましょう!
雨漏りしたらまずどうする?バケツを使った応急処置

雨漏りしたら室内被害の拡大を防ぐために、応急処置を行いましょう。
いくつかある応急処置の中でも天井からの雨漏りに対して、バケツを使うことは有効です。
天井から落ちる雨水がその下の電気製品やカーペット、床などを濡らしてしまうと、2次被害が発生するため、バケツを置いて雨水を受けることができます。
雨漏りをバケツで応急処置するときのポイントと注意点について解説します。
雨漏りをバケツで応急処置するときのポイント

雨漏りをバケツで応急処理するときのポイントを紹介します。
- 水滴が落ちてくる真下にビニールシートとバケツが来るように設置すること
- 屋根裏に入れる場合は屋根裏にバケツを設置すること
天井から水滴が落ちてくる真下にビニールシートをひいて、その上にバケツを置くことをオススメします。
バケツに雨水が溜まってくると滴下したときに水跳ねして、バケツから外へ飛び散ることがあります。
ビニールシートをひいておくことで、飛び散って床が濡れる被害を防ぐことができます。
また、雨漏り箇所の近くに天井点検口があれば、屋根裏にバケツを設置することができます。
屋根裏で雨水を受けることで、天井材が濡れる被害を軽減できます。
雨漏りをバケツで応急処置するときの注意点
バケツに水が溜まりすぎると水ハネで床や周囲に水が飛び散り、被害が広がる可能性があります。
被害拡大防止のため、バケツが一杯になる前に水を捨てるようにしましょう。
雨漏りが長時間続く場合、天井から滴下する位置が移動する場合もありますので、ときどき確認しておきましょう。
屋根裏にバケツを置いた場合、天井・室内への雨漏りがなくなるため、雨漏りをそのまま放置してしまうことがあります。
室内への雨漏りが止まっても、建物内へは浸入しているので、必ず雨漏り修理を行ってください。
バケツでの応急処置について「【雨漏りにすぐに対応できる】バケツを使った応急処置の方法を解説」の記事で詳しく解説しています。
雨漏りしたらまずどうする?タオルを使った応急処置

雨漏りの応急処置としてタオルや雑巾を使うことがあります。
雨漏りで床や家財道具が濡れたときはそのまま放置せず、タオルや雑巾で早く吸い取ることをオススメします。
床材が木材だとシミ・変色しやすいので、タオルや雑巾でふき取りましょう。
また、台風などの風雨の吹き込みによりサッシの下レールや枠の隙間から浸入することがありますので、タオルや雑巾をかぶせることでせき止めることができます。
その他には、バケツの中へタオルや雑巾を入れておくことで、雨水が溜まってきたときの飛び散りを防ぐことにも役立ちます。
雨漏りしたらまずどうする?ブルーシートを使った応急処置

雨漏りの応急処置としてブルーシートを使うこともできます。
室内の広範囲で大量に雨漏りが発生しているときは、雨が浸入してきている部分をまるごとブルーシートで覆うことが有効です。
ブルーシートで床や家財道具を保護できるので、雨漏り後の片付けなどが容易となります。
屋外での応急処置となりますが、バルコニーからの雨漏りの場合、バルコニーの床面にブルーシートを敷き詰める応急処置もあります。
一方で、屋根にブルーシートをかける応急処置は、作業中に屋根から滑落するリスクが高いため、DIYで行うことはオススメできません。
雨漏りしたらまずどうする?吸水シートを使った応急処置

雨漏りの応急処置として吸水シートを使うことがあります。
吸水シートは大量に吸水する能力が高いシートなので、雨漏りの雨水なら充分に吸水することができます。
雨漏りがときどき発生する箇所に置いておくと、外出中の雨漏りでも吸水シートがその下が濡れてしまうことをふせいでくれます。
また、シートを置いておくだけなので、邪魔にならないことも使いやすいです。
タオルや雑巾との違いは、吸水シートは保持し続けるので、その下が濡れにくく応急処置としては扱いやすいです。
吸水シートがない場合は、ペットシーツやオムツなどで代用可能です。
雨漏りしたらまずどうする?防水テープを使った応急処置

雨漏りの応急処置として防水テープを使うことがあります。
サッシの隙間や周辺の枠から室内へ浸入する場合、浸入箇所へ防水テープを貼ることで雨水浸入をふせぎ、応急処置となります。
また、屋外での使用となりすが、外壁・ベランダなどの破損や劣化した場所に防水テープを貼ることで、雨漏りを防ぐ可能性があります。
接着面をきれいに掃除して、しわなく密着させることが重要です。
防水テープはあくまでも応急処置で、修理前には撤去するため、はがしたときに粘着層が残らないタイプを選びましょう。
雨漏りの応急処置について「雨漏り修理や応急処置の重要性!室内でやるべき5つのことを徹底解説」の記事で詳しく解説しています。
雨漏り量が多いとき・広範囲に雨漏りしたらどうする?

雨漏り量が多いときや広範囲に雨漏りしたときは、応急処置を工夫することでバケツをたくさん並べずに済みます。
天井の雨漏り箇所を大きめのビニールシートなどで広範囲に包み込むような形でカバーして、それを下方でしぼり込ませることで、1つのバケツへ集めることができます。
イメージとしては、ビニールシートで漏斗を作り、下方で配管を通して、バケツへ流すことでスッキリした応急処置となります。
店舗や施設などの雨漏りに適した応急処置となります。
大きめのビニールシートの代わりに、大きめのゴミ袋でカバーして、下に穴を開けて排水することも可能です。
雨漏りを見つけたらどうする?原因調査の方法

雨漏りを見つけたら、雨漏り調査をして原因追及してから、それを直す雨漏り修理をすることが基本です。
雨漏り調査の方法はいくつかありますので、主なものを紹介します。
- 目視調査
- 散水調査
- 赤外線サーモグラフィ調査
- ドローン撮影調査
- 解体調査
次の章から詳しく解説していきます。
雨漏りを見つけたらどうする?目視で原因調査

雨漏り調査の手法の1つ、目視調査について解説します。
目視調査とは、室内の雨漏り箇所と屋外を直接確認し、写真撮影して原因を推測する方法です。
雨漏り調査の基本であり、劣化している場所や不具合箇所、屋外の隙間などを目視で探します。
目視調査は調査員の経験や勘に左右される手法とも言えます。
雨漏りを見つけたらどうする?散水で原因調査

雨漏り調査の手法の1つ、散水調査について解説します。
散水調査とは、目視調査で見つけたあやしい箇所へ、ホースで水をかけて促進試験的に雨漏りを再現し、浸入口を特定する方法です。
散水調査は水をかける勢いや量、角度などで漏れるかどうか変わってきます。
雨漏りしたときの降雨条件を把握した上で、散水の仕方を変更する必要があります。
散水調査も調査員の技量によって、結果が左右します。
雨漏りの散水調査について「散水調査の方法とは?調査のポイントや費用を徹底解説」の記事で詳しく解説しています。
雨漏りを見つけたらどうする?赤外線サーモグラフィで原因調査

雨漏り調査の手法の1つ、赤外線サーモグラフィについて解説します。
赤外線サーモグラフィ調査とは、赤外線カメラを使用し、建物内外の温度差から雨水影響を確認する方法です。
赤外線カメラは建物内外の表面温度を撮影できますので、建物の仕様を考慮しながら雨水による温度差を見つけて原因を探ることができます。
赤外線サーモグラフィーによる雨漏り調査について「4つの雨漏り調査方法の中の「赤外線サーモグラフィーによる調査」をご紹介いたします!」の記事で詳しく解説しています。
雨漏りを見つけたらどうする?ドローン撮影で原因調査

雨漏り調査の手法の1つ、ドローン撮影について解説します。
ドローン撮影調査とは、屋根など高所をドローンで撮影し、肉眼で確認できない箇所を調査する方法です。
急勾配屋根、3階建て以上の建物などでは、目視調査するにも足場設置、高所作業車などが必要となります。
ドローンで高所を撮影することで、比較的に安価で目視調査を行うができます。
撮影した写真をもとに、原因を推測することになりますので、解析する能力が必要な調査となります。
雨漏りを見つけたらどうする?解体で原因調査

雨漏り調査の手法の1つ、解体調査について解説します。
解体調査とは、浸入経路不明の場合に天井・内壁を開口(天井や内壁を一部はがす)して調査する方法です。
難しい雨漏りで、散水調査を行う前に解体調査を行っておくと、散水調査の難易度が下がることがあります。
弊社神清の雨漏り調査について「神清の「雨漏り調査」とは?」の記事で詳しく解説しています。
雨漏りしたらどうする?避けたいNG行動

雨漏りした際のNG行動について解説します。
雨漏りの応急処置として、NGな行為は以下となります。
- 室内側だけをコーキングなどでふさいでしまう
- 屋外側の隙間をやみくもにすべてコーキングでふさいでしまう
雨漏りしてくる室内側をコーキングでふさいでしまうと建物内へ浸入した雨水の流れが変わってしまいます。
室内への雨漏りが止まったとしても、建物の雨水浸入は発生しつづけるため、かえって、建物の被害が拡大してしまいます。
また、屋外側の隙間をすべてふさいでしまうと外壁や屋根の排水出口をふさいで、雨漏りが悪化することがあります。
応急処置では「水を受け止めて室内の被害を拡大させない」ことを優先し、原因究明や雨漏り修理は専門業者に任せるべきです。
【まとめ】雨漏り被害が広がる前に、適切に対応しましょう!
雨漏りの応急処置について5つの手法を紹介しました。
雨漏りの応急処置は雨漏り修理ではなく、室内の雨漏り被害の拡大をふせぐことに注力しておきましょう。
その上で、専門業者へ雨漏り調査・雨漏り修理を依頼することをオススメします。
雨漏り修理は原因特定した上で、しっかりと補修することをオススメします。
神清からのお願い
記事を最後まで読んでいただきありがとうございます。
お客様の率直な感想をいただくため「役にたった」「役に立たなかった」ボタンを設置しました。
私たちは、日々屋根にお困りのお客様にとって必要な情報をお伝えしたいと考えております。今後のご参考にさせて頂きますのでご協力よろしくお願いいたします。