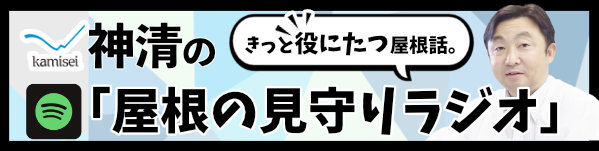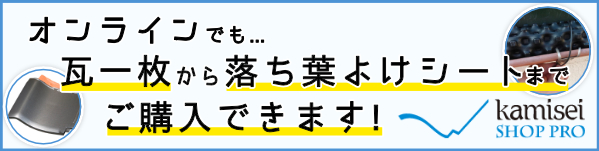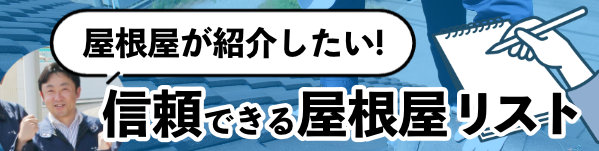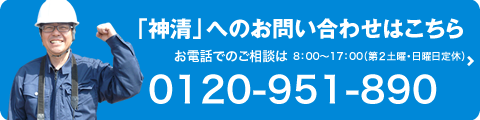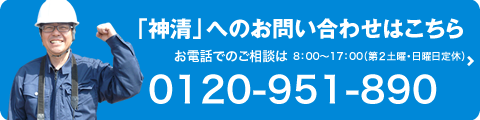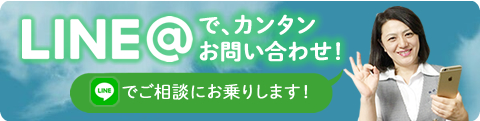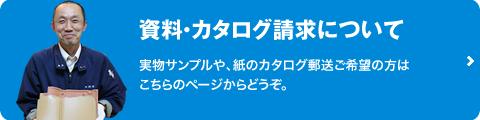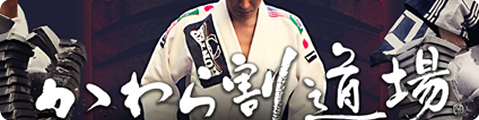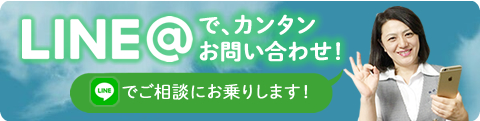目次
雨漏りが発生したときの応急処置の方法

雨漏りが発生したときの応急処置の方法について解説します。
大雨で雨漏りが発生したときの応急処置として、以下の方法があります。
- バケツで水を受ける
- タオルや雑巾で吸水する
- ブルーシートを敷く
- 吸水シートを敷く
- 防水テープを貼る
大雨で雨漏りすると、信じられないほどの水量が天井から雨漏りしてしまうこともあります。
応急処置しないと天井だけでなく、床にも被害が発生してしまうので、応急処置の方法を確認しておきましょう。
次の章からそれぞれについて詳しく解説していきます。
雨漏り発生時の応急処置方法①バケツで雨水を受ける

大雨で雨漏りしたときの応急処置としてバケツで水を受けることがあります。
大雨による天井からの雨漏りをバケツで応急処置することは有効です。
天井から滴下する下にバケツを置いて水を受けることで、床面の被害を軽減できるからです。
雨漏りをバケツで応急処置するときのポイント

大雨の雨漏りでは、天井から水滴落下する場所が時間とともに移動したり、複数個所から落ちたりすることがあります。
そのため、まず、ビニールシートを広げて、その上にバケツを設置するようにしましょう。
滴下位置がずれたり、複数個所となったりして、バケツから外れてもビニールシートで受けることとなり、被害を軽減できます。
また、天井に点検口などがある場合、屋根から滴下している天井上にバケツを置くことで、天井の被害を軽減させることができます。
雨漏りをバケツで応急処置するときの注意点
大雨での雨漏りでは、雨水がバケツに溜まりすぎる可能性があります。
バケツの約半分以上まで溜まると水跳ねするようになり、バケツの周辺や床に水が飛び散り、さらに被害が広がる可能性があります。
被害を広めないためにも、バケツを複数用意して、バケツからの水跳ねが発生するる前に、こまめに溜まった水を捨てるようにしてください。
バケツで応急処置する方法について「【雨漏りにすぐに対応できる】バケツを使った応急処置の方法を解説」の記事で詳しく解説しています。
雨漏り発生時の応急処置方法②タオルや雑巾で給水する
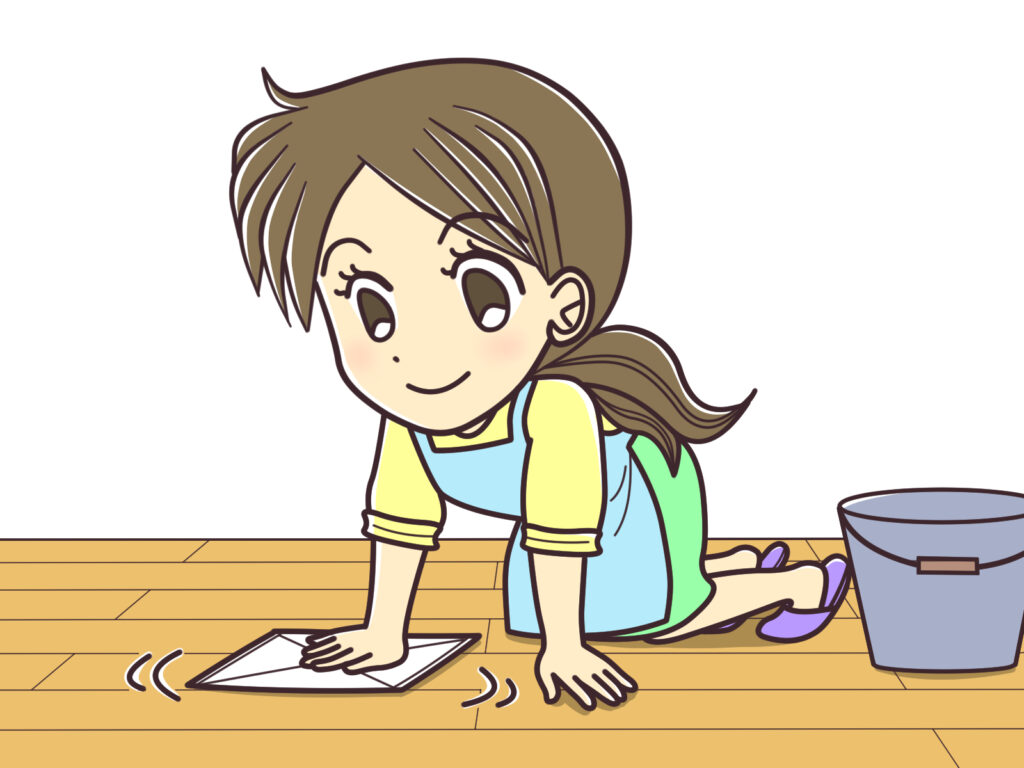
大雨で雨漏りしたときの応急処置としてタオルや雑巾で吸水することが有効です。
タオルや雑巾は、以下のような使い方ができます。
- 天井から落ちてくる雨水を拭き取る
- バケツの中に入れて雨水の飛び散りを防ぐ
- サッシから浸入してくる雨水をせき止める
天井から床に滴下した雨水を拭き取ることができます。
床に雨水を放置すると、床にシミ痕が発生してしまうので、すぐに拭き取ることで被害を軽減します。
バケツの中に入れておくことで、雨水の水跳ねをある程度防ぐことができます。
強風を伴った大雨では、サッシの隙間から吹き込んで浸入することがありますので、タオルや雑巾を設置することで雨水をせき止めることに役立ちます。
雨漏り発生時の応急処置方法③ブルーシートを敷く

大雨で雨漏りしたときの応急処置としてブルーシートを敷くことがあります。
大雨では、室内に複数個所、広範囲で雨漏りすることがあります。
ブルーシートを室内に広範囲で敷くことで、被害を軽減できます。
ブルシートの上にバケツなどを置くことで、雨漏りが終わった後の片付けも用意となります。
バルコニーからの雨漏りの場合、バルコニーの床面にブルーシートを敷き詰める応急処置もあります。
また、屋根にブルーシートをかける応急処置は、作業中に屋根から転落するリスクがあるため、DIYで行うことはオススメできません。
ブルーシートを使用した応急処置について「屋根の一部分の雨漏り対策!ブルーシートを使った応急処置」の記事で詳しく解説しています。
雨漏り発生時の応急処置方法④吸水シートを敷く

大雨で雨漏りしたときの応急処置として吸水シートを敷くことがあります。
吸水シートとは、吸水能力の高いシートのことであり、吸水シート1枚(約400g)で約10リットルの水を5~10分で吸水することができます。
大雨での大量な雨漏りでも、雨水を充分に吸水することができます。
急な雨漏りで吸水シートがない場合は、ペットシートやオムツなどで代用可能です。
タオル・雑巾と違い、吸水シートは水を保持し続け外に漏らさないため、吸水シートを置いたまま外出しても床に害を与えることはほとんどありません。
急な大雨で雨漏りが心配な場合は、吸水シートを日頃から設置しておくと安心です。
雨漏り発生時の応急処置方法⑤防水シートを敷く

大雨で雨漏りしたときの応急処置として防水テープを貼ることがあります。
防水テープとは、防水加工されたテープのことです。
防水テープは、屋根や外壁のヒビ割れや孔などの隙間をふさぐことができるため、浸入口を応急処置的に補修することができます。
必要な長さをハサミやカッターなどでカットして使用できるため、修理場所に合わせたサイズでの使用が可能です。
防水テープを使用するときの主な注意点は以下のことがあります。
- 外壁用や水回り用など用途別に多くの種類があるため、用途に合ったテープを選ぶ
- 応急処置で貼った表面を汚したくない場合、ブチル系ではないものを選ぶ
- 防水テープを貼るときは表面の汚れを落とし、乾燥させた状態で貼る
- できるだけシワ・空気をいれないように貼る
防水テープの中でもアルミ製のテープは耐候性があり、室外でも使用できるのでオススメです。
雨漏り発生時のNGな応急処置とは?

雨漏りしたときの応急処置としてNGなことを紹介します。
大雨で雨漏りしたときにやってはいけない応急処置として、以下の2つがあります。
- 室内側の水滴が落ちてくる箇所をふさぐ
- 室外側の雨水の浸入箇所周辺の隙間をむやみにすべてコーキングで埋める
「雨漏り修理をする前に室内側の水滴が落ちてくる箇所をふさぐ」ことがあります。
大雨で大量に滴下するからと言って、室内の滴下場所をふさいでしまうとその水は別に移動してしまいます。
仮に室内へ雨漏りしなくなったとしても建物内のどこかに水が回り・滞留するだけとなります。
雨漏りは建物の外側の浸入箇所を直すことを優先しなければなりません。
雨漏りの外側の原因がわからないときに、室内側の雨漏り箇所だけをふさいで、一旦、雨漏りから逃げたい衝動に駆られるのはわかります。
ごまかしている間に、建物の柱や金物の劣化が進行してしまい、被害が拡大させてしまう可能性があります。
もう1つは「室外側の雨漏りの浸入箇所周辺の隙間をすべてコーキングで埋める」ことです。
建物の外部の隙間は雨水を排水するために設けてあるものもありますので、外部の構造を理解した上でないと、コーキングしたことで、別の雨漏りが発生するリスクとなります。
コーキングの雨漏り修理について「DIYのNG事例 コーキング雨漏り修理 知らないと…絶対失敗します」の動画でも詳しく解説しています。
応急処置をしないで雨漏りを放置するリスクとは

雨漏りを放置するとどのようなリスクがあるかについてを解説します。
雨漏りを放置すると、以下のようなリスクや二次被害がでる可能性があります。
- 内壁にシミが発生する
- 木材や金属が腐食する
- カビやシロアリが発生する
- 漏電で火災が発生する恐れがある
雨漏りを放置すると、建物の主な構造を担っている木材は腐り、金属は錆びてしまいます。
その他にはシロアリ被害とカビによる被害(健康被害)が心配されます。
木造建物では木材の腐り、シロアリ被害は建物の強度低下につながりますので、もっとも注意しなければならないこととなります。
雨漏りを放置すると、結果として、健康被害が出たり、建物の寿命が短くなったりするのでやめておきましょう。
雨漏りの応急処置をしたあとはどうしたらいいの?

雨漏りの応急処置をしたあとは早めに業者に連絡しましょう。
バケツ等による対処はあくまでも、応急処置です。
応急処置は一時的な対処であり、建物内部への雨漏りを防ぐものではないため、早めに雨漏り修理しましょう。
そのまま、放置していると屋根裏・壁内の劣化など、二次被害にあう可能性が高くなります。
雨漏りを放置することは、割高になりますし、家の寿命を減らします。
部屋に常時、バケツがおいてあることに慣れる前に、早急に雨漏り修理業者に修理を依頼しましょう!
雨漏り修理業者の選び方について「雨漏りを修理できる優良な業者の選び方と特徴を屋根屋が解説」の記事で詳しく解説しています。
普段から雨漏りを防ぐためにできることは?

雨漏りを防ぐために日頃からできることを紹介します。
- 普段から外壁のヒビ割れや屋根のズレなど、家の状態を確認する
- 5〜10年ごとに外まわりのメンテナンスを行う
- 雨樋、屋上、バルコニーなどの排水口を点検・掃除する
- 雨樋に「落ち葉よけシート」を設置する
普段から外壁・屋根・バルコニーに異常がないか確認しておくことで、何か不具合が発生した場合に対応できます。
外装材の種類によって、5~10年程度でメンテナンスが求められるものがほとんどですので、劣化する前にメンテナンスすることでも雨漏りを防げます。
大雨での雨漏りは排水口の詰まりによるオーバーフローの可能性があります。
排水口の点検・掃除を定期的に行うことでオーバーフローを防ぐことができます。

雨樋の破損や外れなどは雨漏りの原因となります。
雨樋の変形・破損・劣化は雨樋の詰まりが要因となることが多いです。
細かい葉やゴミも雨樋に侵入させない「落ち葉よけシート」の設置が雨樋の詰まり対策に有効です。
「落ち葉よけシート」について「雨樋の詰まりは本当に防げる?落ち葉よけシートをDIYで試しに設置してみました!!」の記事で詳しく解説しています。
【まとめ】応急処置のあとは早めに業者に連絡しよう
大雨で雨漏りすると、信じられないほどの水量が天井から雨漏りしてしまうこともあります。
雨漏りの応急処置を行うことで、被害を最小限にとどめることができます。
応急処置は一時的な対処であり、建物内部への雨漏りを防ぐものではないため、早めに雨漏り修理しましょう。
早期に雨漏り修理することが被害を最小限にすることができ、修理費用も安価になるのでオススメです。
神清からのお願い
記事を最後まで読んでいただきありがとうございます。
お客様の率直な感想をいただくため「役にたった」「役に立たなかった」ボタンを設置しました。
私たちは、日々屋根にお困りのお客様にとって必要な情報をお伝えしたいと考えております。今後のご参考にさせて頂きますのでご協力よろしくお願いいたします。